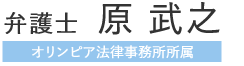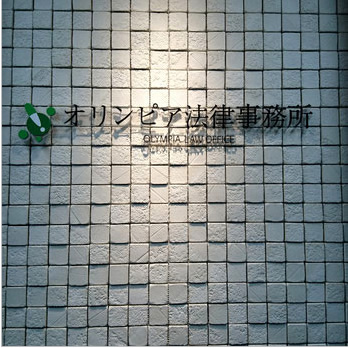就業規則変更の流れ|注意するポイントはある?
就業規則の改訂を行いたいと思った場合には、どのような手続きを踏まなければならないのでしょうか。
この記事では、どのような場合に改訂が行われることになるのかに加え、改訂の具体的な方法について記していきます。
■就業規則とは
就業規則とは、会社のルールを記したもので、労働時間・賃金・退職に関する内容をはじめとして、休日・費用負担・安全衛生に関する内容など、記される分野は多岐にわたります。
就業規則は、労働者が10名以上の場合には作成が義務付けられていますが、中小企業でも80パーセント以上の会社がこれを作成しているため、実質的にはほとんどすべての会社に存在するといえます。
■就業規則を変更する場合
このように会社の根本にも関わってくるため、改訂すれば会社の勤務実態を大きく変えかねない就業規則について、これを変更することになるのはどのような場合なのか、想像がつきづらい場合もあるかと思います。以下、就業規則を変更する場合について見ていきましょう。
●労働関連の法令改正があった時
労働基準法が代表する、労働関連の法令が改正され、従業員保護が強まった結果、就業規則の一部が従業員に不利であることを理由に無効となってしまうことがあります。
このような場合は、就業規則を法令に合わせて改訂する必要があります。
また、最低賃金法の改正により最低賃金が上がったような場合、改正後の最低賃金以下の給料で従業員を働かせている会社については、就業規則の賃金に関する規定を改訂する必要が生じます。
●経営状況が悪化した時
経営状況が悪化した場合、これまで通りの賃金を従業員に払い続けることが難しくなってくることがあります。
そのような場合は、就業規則の賃金に関する規定を変更し、これを下方修正することも必要となってきます。また、これまで従業員に与えられていた手当を廃止することも考えられます。
もっとも、就業規則の改訂により従業員が不利になってしまう場合には、変更に合理性が求められることになります。
●在宅勤務(テレワーク)制度や変形労働時間制を導入するとき
近年増えてきている在宅勤務制度などを導入するときにも、これまでそのような慣行がなかった場合には就業規則を改訂して、その詳細について定める必要があります。
このように、時代や業務形態の変化に合わせた改訂が行われることも考えられます。
■就業規則を改訂する方法
それでは、規則を改定するには具体的にどのような方法を取ることになるのでしょうか。
以下、順を追って見ていきましょう。
●経営陣による承認
就業規則を変更したい場合、まずは草案をまとめることになります。これは総務部などが担当することが多いです。
また、正社員の他に非正規雇用の者が働いている場合には、適用を受ける従業員の範囲についても決定する必要があります。
草案が出来上がったら、法律に違反していないかのチェックを行います。これは法務部など、法律を専門とする者ないし部署が行います。
チェックが終了した就業規則は、主として取締役会に提出する形で、経営陣の承認を受けることになります。
●意見書の作成
改訂された就業規則は、労働基準監督署庁に届け出ることが必要となりますが、その際には労働者の意見書を提出することが必須となるので、これを作成します。
意見書には、労働者の過半数の代表者の意見をまとめることになります。
過半数が加入する労働組合がある場合には、ここでいう代表者は当該労働組合の代表者を指すことになるため、その意見をまとめれば問題ありません。
一方で、そのような労働組合がない場合には、労働者間の協議や投票によって、代表者を決めていくことになります。
前者の場合は労働組合の名前を、後者の場合は代表者の選定方法を記載する必要があります。
この際、従業員の代表者が改訂に同意している必要はありません。あくまで意見を聞き、書面の形にまとめることが必要となるのみです。
もっとも、労働者の納得を得るために誠実な説明を尽くすことは、後のトラブルを防ぐためにも大事になってきます。
●就業規則変更届の作成
次に、改訂の内容について記した就業規則変更届を作成します。
変更届については、決まった様式がないため、ゼロから作成することも可能ですが、労働局のホームページにて入手することのできるひな型に合わせて書くことをお勧めします。
変更届には主な変更点を記載すれば足りるので、就業規則のうち改訂があった場所だけを記載して提出することができます。
●書類の届出
作成した意見書および就業規則変更届を、労働基準監督署の窓口へと提出します。これらは2部ずつ用意する必要があるため、注意してください。
また、窓口に赴かずとも、郵送による届出を行うことも可能です。
これによって、就業規則の改訂に必要な手続きは完了します。
就業規則の変更があったことは、従業員に周知することが必要になります。その方法としては、主に掲示や書面による交付、データ化などが考えられます。いずれにしても、従業員が就業規則の変更に気が付き、いつでも変更後の規則を確認できるようにしておくことが大切です。
労働問題については、様々な法律問題が発生する可能性があります。問題が大きくなり、会社に大きな影響を与えたり、思うように経営が進まなくなったりする事態を避けるためにも、弁護士への相談をお勧めしています。
オリンピア法律事務所は、名古屋市を中心に、愛知県全域にお住いの皆様から、使用者側の労務問題、企業法務、債権回収・損害賠償など、幅広い分野にかかるご相談を承っております。お困りのことがございましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。最適な解決方法をご提案させていただきます。
当事務所が提供する基礎知識
-

カスタマーハラスメン...
昨今、さまざまなハラスメントが問題視されています。パワハラ、セクハラが代表的ですが、カスタマーハラスメント、略してカスハラも問題視されています。 このページでは、カスタマーハラスメントとは何か、訴える前にするべきことをご […]
-

正しい退職勧奨の進め...
労働契約においては、労働者と使用者は契約当事者として本来は対等な地位にあります。しかし、一般的な力関係は使用者が上であり、労働者が下であることがほとんどです。労働法はこの力関係を本来あるべき姿に戻すべく、労働者の地位を保 […]
-

労働組合から団体交渉...
団体交渉とは、労働者が労働組合などを通して集団として、使用者との間で、労働条件やその他労使関係のあり方について交渉することです。団体交渉は労働者に日本国憲法や労働組合法で保障されている労働者の権利であるため、使用者がこれ […]
-

パワハラによる社員の...
パワハラによる退職は会社都合になる場合があります。この記事では「自己都合と会社都合で退職した場合の違い」や「パワハラによる退職を会社都合にする方法」などを解説します。パワハラとはパワハラとはパワーハラスメントの略で、職場 […]
-

従業員が社用車で事故...
社用車で事故を起こした場合、会社はどのように対応するべきでしょうか。今回は、従業員が社用車で事故を起こした際に会社が対応すべきことについて解説していきたいと思います。会社の取るべき対応について従業員から事故の報告を受けた […]
-

体調不良(メンタルヘ...
ストレスからうつ病などの病気に罹患し、メンタルヘルス不調に陥った労働者は、休職を検討することが多く存在します。休職には、法律上の規定が存在しないため、就業規則に規定を設ける必要があります。具体的な規定に関しては、対象の社 […]
よく検索されるキーワード
弁護士紹介

原 武之Takeyuki Hara
弁護士登録後から労務問題と倒産問題を中心に扱ってきましたが、どんな時にも意識するのは、受動的に対応するのではなく、主体的に積極的に対応していくことであると思っています。
問題が発生してから動くのではなく、問題発生を予見し、依頼者の方が目指す方向に向けて解決策をどこまで提示することができるか、それを常に自問して業務を行っています。
- 所属
-
- 愛知県弁護士会
- 経歴
-
- 兵庫県西宮市出身
- 兵庫県私立滝川高校卒業
- 平成12年 早稲田大学法学部卒業
- 平成15年 弁護士登録(56期 第二東京弁護士会)
- 森・濱田松本法律事務所入所
- 平成18年 川上法律事務所移籍独立(愛知県弁護士会に登録換え)
- 平成21年 川上・原法律事務所に名称変更
- 平成29年2月 オリンピア法律事務所 パートナー
事務所概要
| 弁護士 | 原 武之(はら たけゆき) |
|---|---|
| 所属事務所 | オリンピア法律事務所 |
| 所在地 | 〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内1-17-19 キリックス丸の内ビル5F |
| 連絡先 | TEL:052-201-7728 / FAX:052-201-7729 |
| 対応時間 | 平日 9:00~18:00 |
| 定休日 | 土・日・祝日 |